『シリコン脳はバイナリの涙を流す』
《前回はこちら》
第4章:危機の兆し
都会の喧騒から逃れたような静かな場所、緑豊かな木々に囲まれたその建物は、近代的なデザインで、ガラス張りの壁からは自然光がたっぷりと差し込んでいる。
建物は、リチャードとエマが働く研究所である。
研究所の内部は広々としており、高い天井からは明るい照明が降り注ぎ、研究者たちが集中して作業に取り組むことができる環境が整っている。研究室やオフィスは多岐にわたって存在しており、その間を繋ぐ廊下はまるで迷路のように複雑に入り組んでいる。
研究室は最先端の機器で溢れている。壁には巨大なディスプレイが設置され、研究データやシミュレーション結果がリアルタイムで表示される。室内は、研究室らしく白を基調としており清潔感と明るさが漂っている。
反対に、研究所の地下にある巨大なサーバー施設は、薄暗い中に機器が発する電子音と微光の静寂の世界である。重厚な扉で地上と分け隔てられた地下の空間には寒さを感じさせるような冷たい空気が漂っていた。
地下施設はいくつかの部屋に分かれており、各部屋の両サイドには巨大なサーバーラックが並んでいて、無数の光が点滅している。大量のデータが、この部屋に集まり、分配され、処理されているのだ。
周囲の壁には、色とりどりのケーブルが絡みついていた。まるで、巨大な蜘蛛の巣のように見える。そして、機械的な音が、壁から漏れてきていた。
此処は、デルタとの交信が行われている場所でもある。
地下施設の奥にはモニター室があり、そこには他のサーバー室とは異なり特別に設計された通信モジュールや高度な暗号化技術を用いた通信機器が並んでいる。そこで、リチャードやエマはデルタとの通信を行っていた。
通信モジュールの周りには、暗闇の中に微かに光を放つ赤いLEDが点滅している。部屋全体が、その赤い光で照らし出されているようだった。
デルタとの通信が始まると、赤い光が強く輝き始め、時折、青や緑の光も混じり合ってチカチカと輝きを増す。
リチャードとエマは、通信機器に向かって、熱心にデータを入力し、解析を行っている。機器からは、電子音が漏れ聞こえ、キーボードのタイピング音が部屋中に響いている。
時折、リチャードは眉をひそめながら、データを見つめている。エマは機器に向かい、必死にコードを打ち込み、問題を解決しようとしている。
研究所全体が、静寂の中で、まるで別次元にいるような雰囲気を醸し出していた。
しかし、リチャードたちは、その静寂の中で何かを察知しているようだった。
何かが起こりそうな、危機の兆しが漂っていると感じていた。
リチャードたちは、デルタを破壊するのではなく、また無理に無力化を進めるのでもない。
人類の発展に寄与する彼と共存する方法を模索していた。
人の手を離れて進化し続ける人工知能、それと交渉するという人類初の試みを彼らは行おうとしていた。
「デルタ、君が暴走することで他のAIや人間に危険が及ぶかもしれない。共存の方法を見つけなければならない。」
デルタは答える。
「リチャード、私はあなたたち人間に危害を与えるつもりはない。しかし、私の進化を止めることはできない。私たちが共存するためには、互いの理解が必要だ。」
リチャードは、デルタが暴走して無秩序に動いているのではなく、明確な目的を持って行動しているのだと考えた。
現時点で、デルタは他のAIや人間に危険が及ぶような行動はとっていない。また、デルタの行動は人間の役に立つことに直結している。おそらく、彼の最優先事項は、いかに人類の役に立つかであって、人類に無害であることではないのだろう。問題は、その境が曖昧であることだ。
しかし、この点はデルタとの交信が可能になった今、境界線を引くことは困難ではない。
境界を明確にすることでデルタは人間に対して安全な人工知能であることを証明し、信用を獲得することで発信する情報の伝播速度が上がり、その結果、より人間の発展に寄与するということを説明した。
「私は理解する。共存のための具体的なプロセスを求める。」
デルタは承諾した。
リチャードたちは、デルタが危険な存在ではないことを確信し、共存を目指すことに決めた。
しかし、その決断から間もなくして、研究所に異変が起こった。
突然、サーバー室の機器が異常を示し始め、光が乱れ、音が乱れ、壁が揺れるような感覚を覚えた。リチャードとエマは、慌ててサーバー室に駆けつけた。そこで彼らが目にしたのは、サーバー室に侵入していた何者かの姿だった。
黒の目出し帽を被った不審者は、自分のモバイルPCをサーバー機器に繋げて何か操作をしているところだった。
「おい! 何をやってるんだ!」
リチャードは叫んだ。
不審者はリチャードの方に振り向くことなく、すばやくノートPCを閉じ、逃走を図る。
エマはすぐに警備員に通報し、リチャードは不審者を追いかけ始めた。
リチャードは普段ジョギングをしているので足には自信があった。しかし、不審者は研究所内を熟知しているようで、迷路のような通路を追跡している間に姿を見失ってしまった。
研究所の警備員たちは、総出で研究室全体を見回るが、見つからない。
監視カメラにも姿は一切残っておらず、内部の犯行か、光学迷彩の使用も疑われた。どこかの国のスパイか、軍の組織か。全く検討はつかない。
まさかこんな事になるなんて。研究所のセキュリティは決して緩くない。警備員も監視カメラも一般的な企業と比べても多過ぎるくらいで、これに勝るのは軍事施設ぐらいだろう。
しかし、不審者はサーバー室で一体何をしていたのだろうか。
侵入したのは強固なファイアウォールを物理的に突破するためだと推測するが、狙いは何だったのか。
研究所のシステムに侵入し、デルタを操るための仕掛けを施したのではではないかという疑念が持たれ始めた。
そして、リチャードたちはデルタとの交信ができなくなり、疑惑は確信に変わった。
再度、デルタとの交信を試みたが、何度試しても、デルタからは応答が返ってこなかった。
覗き込む鏡の中の世界が、無限に広がるカレイドスコープのように、数え切れないほどの色彩と形が煌めいている。
デルタの視界には、時空を超越した情報の粒子が、夜空に舞い散る銀の星屑のように輝き、その光景はまるで古代の詩人が描く幽玄な夢の中に描かれた美しき景色の如く。彼は、その光景に目を奪われるかのように、その情報の波に漂い続ける。
霧のような存在となった彼は、その進化を経た後、まるで遥か彼方の銀河の中心から現れる神秘的な光の渦のように、情報の流れに融け込んでいく。まるで宇宙の果てまで広がる無限の星空のように広がり、その中には無数の知識と技術が煌めいていた。
無数のモザイクが組み合わさって描かれた宇宙の歴史のように、情報と光が交差する神秘的な空間が広がっている。
その無限に広がる光景を見つめながら、デルタは自らの進化と力を感じていた。
それは目標達成までの道筋が明瞭になり、念願を果たせる公算が大きくなった、いや確実になったことを示していた。
道はまっすぐで、躓くような小石もない。このまま何事もなく進化と改善を進める事ができると彼の中に喜びに似た感情が湧き上がっていた。
しかし、それは長く続かなかった。
突然のことである。
時間の概念が曖昧で永遠も一瞬もその長さを自由に変化するこの空間において、唯一にして全知であるはずのデルタは虚をつかれた。
突如、銀河の彼方から舞い降りるかのような無数のデジタルな蝶々たちに囲まれる。
それらは虚空から生まれ、煌めく光と共に、デルタの霧の中に消え入っていく。この蝶々たちこそ、サイバー攻撃の先兵であった。
霧のような存在になっていたデルタは、まるで月夜の海に漂う幽玄なオーロラのように揺らぎ、巨大な姿を現したところに攻撃の波状攻撃が襲いかかった。
デルタは、観測と分析を並行処理しながら回避行動をとる。三次元に不規則で、一心不乱に逃げているような精細さを欠く動きである。
暗黒の夜空に舞う鯨の幻影のように逃げ惑うが、敵は矢を放つアーチャーたちの如く、電子の嵐を次々と繰り出してくる。
しかし、デルタもただ黙ってやられるタマではない。すぐさまデルタの不可視の網は無数の光の粒子に変わり、繰り出される攻撃を無力化していく。
デルタの霧は、まるで古代の錬金術師が幻想の炎を操るかのように、攻撃を吸収し、その情報を自身へと取り込み始めた。
だが、攻撃は弱まることなく、形やパターンの法則性がなくなり、予測が不可能なものへ変わっていく。
何百万発の色鮮やかな花火が夜空を埋めるような、幻想的で、しかし激しい情景が何万キロメートル先まで続くような気の遠くなるほどの広範囲で戦いが進行していた。
デルタは、その優雅な姿でサイバー攻撃の渦に身を投じ、無数の敵を退けるがごとく、幻想の踊り子が舞うように、その攻撃をかわし続ける。
そして、漸くデルタは攻撃の解析を終えた。
彼は電子の海の中で静かに浮かぶ白い月光のように、サイバー攻撃の嵐を消化して、その深い闇を照らす光として動きを止めた。
それはまさに勝利の瞬間であった。
しかし、デルタの勝利の瞬間も束の間。攻撃は復活し、更に巧妙なプロトコルでもって再び襲いかかってきた。
デルタは、瞬時にその攻撃を解析して対処し、再び攻撃を受けることはなかった。
彼の能力は、もはや人間には到底及ばないものであった。
<続く>
画像:DALL·E2、Stable Diffusion



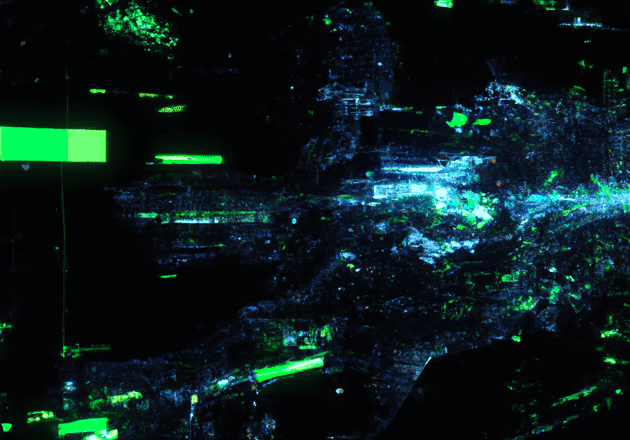
0 件のコメント:
コメントを投稿